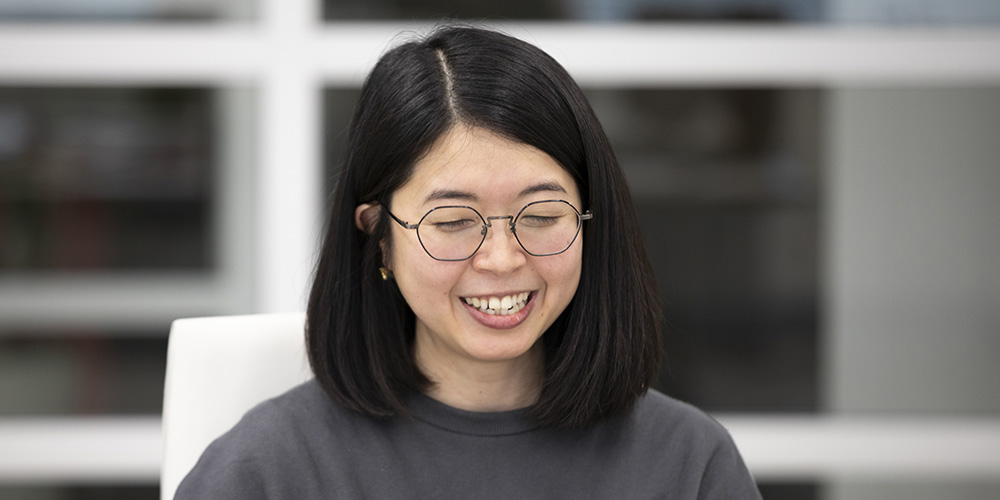
現代の生き方のヒント
「PLOTTER MAGAZINE」
[Interview No.012]
さまざまな世界において活躍する「PLOTTER」の行動力は創造性に溢れています。
「PLOTTER MAGAZINE」は、彼らの考え方や価値観を通して、過去から今までの歩みをたどり将来をポジティブな方向に導く変革者たちを応援します。
私たちが創るツールと同じように、ここに紹介する「PLOTTER」の物語が、みなさんにとってのクリエイティビティのヒントになれば幸いです。
12人目となるInterview No.012のPLOTTERは、ドキュメンタリーディレクターの高木 つづみさんです。
1本の番組は1通のラブレター。
自分が見た美しい世界を伝えるために、
今日もカメラを回し続ける。
ビデオカメラを片手に、高木つづみさんは国内外を飛び回る。アフリカに生息する巨大なナイルワニ、タンザニアの難民キャンプで奮闘する看護師、カンボジアの伝統的な絹織物の復興に尽力したテキスタイルデザイナーなど、高木さんがレンズを向けて見つめた世界は、驚き、発見、感動といった視聴者の“気付き” を呼び起こす。
生まれたのはアメリカのニュージャージー州。1 歳半の時に日本に戻るも、小学校、中学校、高校時代をベルギーで過ごし、絵を描くことが大好きだった少女はイギリスの美術大学へ進学する。「日本人でありながら、日本のことを知らない」と、大学卒業後の2005年に帰国。以来、日本を生活の拠点とし、現在は『ワイルドライフ』(NHK)、『ダーウィンが来た!』(NHK)、『情熱大陸』(MBS)、National Geographics などの人気番組に携わるフリーランスのドキュメンタリーディレクターとして、精力的な活動を続けている。
高木さんの第一印象は「柔らかな口調と穏やかな微笑みが心に残る、小柄でかわいらしい女性」というものだ。会話を重ねるごとに、その小さな身体に内包される、真っ直ぐなエネルギーや凛とした姿勢、芯の強さに魅了されていく。
――イギリスの美術大学では、何を学ばれていたのですか?
専攻はファインアートの4D です。写真や絵画が2D、彫刻が3D、4D は映像やパフォーマンスといった分類ですね。私は小さい頃からずっと絵を描いているんです。ベルギーで育ったため日本語と英語が話せるのですが、自分の中では両方のレベルが低い。だから言葉では伝えきれない思いを、絵に託していたのだと思います。

―なぜ絵ではなく、映像の道に進まれたのでしょうか?
たぶん自分の絵に飽きたんでしょうね。父がガジェット好きということもあり、高校時代から自分でビデオカメラを回していたんです。緻密なスケッチが描けなくても、映像ならきれいかつ素早くその場を記録できる。そして何より映像が楽しかったんです。幼稚園を訪ねて子どもたちが見た夢がモチーフのアニメーションを制作したり、イギリス国内で起きていたデモを映像に収めたり、大学の卒業制作でも映像作品をつくりました。それを映画祭に出品したところ、「政治ドキュメンタリー」というジャンルでの扱いとなり、そこで「私の作品はドキュメンタリーなんだ」と気付いたんです。
とはいえそんなことはすっかり忘れ、大学卒業後はまず日本に帰ってきました。私は日本人なのに、日本のことを一切知らなかったんです。留学される方が海外に憧れるように、私は日本に憧れていたんですよね。帰国後はデジタルハリウッドの夜間コースで2 年間映像を学び、昼間はホラー映画の現場で、ラインプロデューサーのバイリンガルアシスタントとして働いていました。そんな中、父の知人の紹介でドキュメンタリーのプロデューサーと出会い、報道系ドキュメンタリー番組をつくる「メディア・メトル」という制作会社に入社することとなったんです。

――制作会社での勤務を経て、ドキュメンタリーディレクターとして独立されたきっかけをお聞かせください。
「メディア・メトル」では『未来世紀ジパング』(テレビ東京)や『ガイアの夜明け』(テレビ東京)など、さまざまな番組を担当させていただいたのですが、ある時『ワイルドライフ』の企画会議で、私の企画が通ってしまったんです。まさか通るとは思っていなかったナイルワニの生態に迫る企画なんですけど、その撮影でタンザニアのセレンゲティ国立公園を訪れた際に気付いてしまったんですよね。「永遠の平原」を意味するセレンゲティの大地に立ち、「私はいま、やりたいことをやるために、いたい場所にいる。この状態がすごく好きだな」って。それで会社を辞めてしまいました(笑)。
―なんと、急展開ですね(笑)。
ナイルワニの撮影以降、私は動物の企画ばかり出していたんですよ。でも主に経済番組を担当していた自分が本来提案しないといけないのは、経済情報の最先端。動物の企画はなかなか通らないですし、この気持ちのまま会社に残っても迷惑をかけてしまいます。だから退社するのがベストだろうと。「メディア・メトル」には大変お世話になりましたし、いまでも心から感謝しています。

――テレビ番組のディレクターさんの仕事は、肉体的にも精神的にも非常にハードだと思うんです。職業そのものを変えようと思ったことはなかったのですか?
確かに、仕事はハードですね。「辞めたい」と思うことはしょっちゅうです(笑)。だけど自分たちが撮影して編集した映像が公共の電波にのり、多くの方に観ていただける快感を知ると、辞められなくなるんです。視聴者の方から届くコメントの存在も大きいですね。『情熱大陸』で世界最大級の難民キャンプで活動されていた看護師の大滝潤子さんを撮影した時は、「看護師になりたいと思いました」という言葉をいただいたり、『ダーウィンが来た!』でクリップスプリンガーを紹介した時は、男の子がクリップスプリンガーの絵をハガキに描いて送ってくれたり。もう泣けてくるんです。

――高木さんが手掛けた番組が、誰かの人生を変えるきっかけになることもあるのでしょうね。
人生を変えるとまではいかなくても、私自身が感動したものを、番組を通じて共有できていることは確かです。もしかしたら絵を描くのと同じ気持ちなのかもしれません。芸術家は常に己と戦い、表現を続けているのだと思います。私にとっての絵はある種の自己満足でしたから、己との戦いもないまま飽きてしまいました。絵を描くことは呼吸のようなものなので、いまでも描きますよ。でもアーティストに戻るとするなら、60 歳、70 歳くらいですかね。私の中身はまだまだ空っぽなので、いろんな世界を見て、いろんなものを吸収しておきたい。いつか私自身が自分の中を見たくなるくらいに。会いたい人に会える、話したい人と話せる、聞きたいことを聞ける、行きたい場所に行ける、それがディレクターの仕事です。早起きは苦手ですが、素晴らしく美しい日の出をみんなに観てもらうためだったら、夜明け前に出発することも全く苦ではありません。

――ドキュメンタリーディレクターとして、高木さんが映像に残したいものは何ですか?
やっぱり動物ですね。動物への興味が増したのはセレンゲティを訪れてからですが、もともと動物番組は好きだったんです。それを自分がつくれると思ったら、ワクワクがとまらなくて。見たことも聞いたこともない動物を撮影したい。自然と戦っている感じもすごく好きなんです。余談ですが私の結婚式もセレンゲティで行ったんですよ。マサイ族の方に祝福していただく、マサイ式で(笑)。
――それはすごい! まさに一生の思い出になる結婚式ですね。動物に限らず、高木さんは人物にフォーカスを当てた作品も多数制作されています。
出会ってしまうんです。本当に素敵な方に。私は自分の居場所を見つけた方に憧れているんです。そんな方に出会った時、企画を書くようにしています。
カンボジアのクメール織物の復興と活性化に取り組まれた森本喜久男さんもその一人。森本さんをご紹介する『情熱大陸』が放送された数ヵ月後にご逝去されたのですが、取材に入った時点で森本さんはすでに余命宣告を受けている状態でした。動くのもお辛い状況だったと思うんです。ですが「最近の若者は自分に自信がないという。そんなことはない。好きなことをやればいいんだと伝えたい」というお考えのもと、「あなただったら、私の人生の最後を全部撮っていい」と言ってくださって。約6ヵ月の取材期間の間に、深いお話をたくさんお伺いすることができ、言葉では言い表せないほど貴重な経験をさせていただきました。

――番組を拝見しました。森本さんの暖かさや包容力、そして素晴らしい人格者であることが伝わってきました。
ありがとうございます。私にとっての番組は、取材させていただいた方への“ラブレター”なんです。振られたことももちろんありますよ。でもその方の魅力をどうやったら伝えられるのかを必死になって考えて、自分がお聞きしたことや見せていただいたことを必死になって映像にまとめる。一度撮らせていただいたら、その方とずっと関係を続けられる作品を作ろうって誓ったんです。私は海外で育っているので、日本では当たり前のことも新鮮に映ります。同時に帰国後15 年間は日本に住んでいますから、日本人の感覚も身についてきました。だからきっと海外の方も日本の方も「一緒に仕事をしよう」と言ってくださるのだと思うんですね。自分の意見をもちつつ、求められることをしっかり届け、すべてを吸収し、いつか絵に昇華できたらいいなと考えています。


――これから手掛けられる映像作品も、いつの日か拝見できる絵画作品も楽しみしています。ご趣味のひとつである銅版画の作品も素敵ですね。
銅版画を制作する時間は癒しですね。私には時間軸が2 つある気がしていて、仕事や生活は現在を生きている時間、絵を描くのは自己の世界に没頭できる時間。昔からそうなんですけど、絵を描いていると自分が解放されるんですよ。いつも私を支えてくれた絵は、絶対に手放してはいけないもの。どんなに忙しくても、定期的に通っている「銅夢版画工房」の展覧会には必ず出品するようにしています。

――「銅夢版画工房」は大切な場所になっているのですね。最後に、高木さんにとって「PLOTTER」とは、どんな人間像だとお考えでしょう?
もし私が「PLOTTER」と形容できる人間であるならば、やりたいことをやっています。むしろやりたいことしかできません。それだけは確実に言えると思います。
【髙木 つづみ ・ Director / Producer】
アメリカ・ニュージャージー州生まれ。 CSMUniversity of the Arts London, BA Fine Arts 4D卒。小中高とベルギーで過ごす。日本人だが日本を知らないことに気づき2005年に帰国。以来15年間日本在住。現在は、フリーランスでドキュメンタ
リーを中心に映像に携わっている。東アフリカを中心に世界を飛び回り取材。代表作は、ワイルドライフ(NHK)、ダーウィンが来た(NHK)、情熱大陸(MBS)、National Geographic、等々。


